皆さんはどんなイヤホンを使っていますか?イヤホンを選ぶ上で何かこだわりはありますか?
私にとってイヤホンは「外出先で音楽を聴くためのツール」という認識が強く、長らく音質を重視したカナル型ワイヤレスイヤホンを愛用してきました。耳の穴に密着するカナル型は、外部の雑音を最小限に抑え、豊かな低音を響かせてくれるため、音楽鑑賞にはこれしかない、と信じて疑いませんでした。
しかし、そんな
カナル型イヤホン“信者”だった私の常識を覆したのが、今回ご紹介する骨伝導イヤホン「AfterShokz(アフターショックス)」です。一般的なイヤホンとは全く異なる特性を持つ骨伝導イヤホンは、その聞こえ方も独特です。テレワークが普及し、自宅で働く時間が増えたことをきっかけに、この骨伝導イヤホンを使い始めたのですが、これが想像以上に快適で、今ではテレワークに欠かせない存在となっています。
この記事では、カナル型一筋だった私がなぜ骨伝導イヤホンを選ぶに至ったのか、その経緯を交えながら、AfterShokzがテレワークにおすすめである理由を詳しくご紹介していきます。
骨伝導イヤホンとは
そもそも「骨伝導イヤホン」とは、どのような仕組みのイヤホンなのでしょうか。まずは簡単にご紹介します。
一般的なカナル型やインナーイヤー型のイヤホンは、音の振動(空気振動)を耳の穴(外耳道)から鼓膜に伝え、その振動が内耳に届くことで音を認識しています。
それに対して、骨伝導イヤホンは耳をふさがず、耳の前にある頬骨や側頭部の骨に振動を直接伝える仕組みになっています。骨を介して内耳(蝸牛)に音の情報が届くため、鼓膜を使わずに音を聴くことができるのが最大の特徴です。
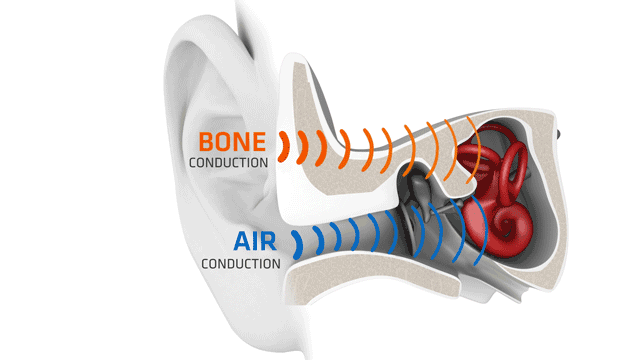
このため、耳を塞がないことで周囲の音を聞きながら音声を聴ける、長時間使用しても耳が痛くなりにくいといったメリットがある一方で、通常のイヤホンに比べると仕組み上、音質や低音の再現性は通常のイヤホンより劣る場合があったり、音漏れが生じやすいといったデメリットも存在します。
骨伝導イヤホン のメリット
ここからは、骨伝導イヤホンの一番の特徴である、耳の穴を塞がないことによるメリット詳しくかいていきたいと思います。
周囲の音が聞こえる
骨伝導イヤホンは耳の穴を塞がないため、音声と一緒に周囲の音も同時に聞き取ることができます。
たとえば、隣にいる家族や同僚から話しかけられた際にも、音楽や会議音声と並行して自然に相手の声が聞こえるため、状況に応じたスムーズな対応が可能です。音楽を再生している場合でも、BGMのように流れながら周囲の音と共存するため、常に周囲の状況を把握しやすいのが特徴です。
この点はテレワークでの活用に非常に向いていると感じます。
たとえば私自身は基本的にリモートワークですが、以前は電話の際にイヤホンを付け、会議が終わったら取り外して充電し、急な電話がかかってきた時には再度装着する、という作業を繰り返していました。しかし骨伝導イヤホンに変えてからは、朝から装着したままで一日中使用できるため、電話がかかってきてもすぐに対応でき、作業中には音楽を流しつつ家族の声も聞き取れるなど、非常に快適な使い方ができています。
また、屋外での使用時にも安全性が高まるメリットがあります。
たとえば散歩や通勤中に使用している場合でも、後方から近づいてくる車や自転車の音など、周囲の環境音をしっかり把握しながら音楽や音声を楽しめるため、一般的なカナル型イヤホンより安心感が高まります。
加えて、多くの骨伝導イヤホンは長時間のバッテリー駆動に対応しており、私が使っているモデルでは最大16時間(音楽再生は約8時間)程度の連続使用が可能です。そのため、朝から夜までほぼ電源を入れっぱなしでもバッテリー切れを気にせず使える点も、大きな魅力といえるでしょう。

耳穴が蒸れてかゆくならない
これは私自身の悩みでもあるのですが、 カナル型イヤホンを長時間装着していると、耳の中が蒸れてかゆくなってしまうことがあります。とくに1時間以上つけていると、イヤーピースが耳穴に触れている部分がムズムズして不快感を覚えるようになります。
もちろん、イヤーピースの素材や形状によって装着感は異なりますし、耳の形にも個人差があると思います。
カナル型イヤホンは、耳穴にしっかり密着することで低音・高音をしっかり届けることができる構造なので、密着が甘いと音質が落ちてしまいます。ですから、音質を優先してイヤーピースと耳穴が密着している状態で長時間装着したままでいると、耳穴の蒸れやかゆみが気になる場面がどうしても出てきます。
その点、骨伝導イヤホンは耳穴に一切触れず、こめかみや頬骨に軽く接するだけなので、長時間つけていても不快感がほとんどありません。「骨に直接振動が伝わる=こめかみに押し当てて痛いのでは?」と最初は不安でしたが、実際に使ってみると、程よいフィット感がありながら圧迫感は感じませんでした。
ずれ落ちない程度にしっかりと装着されていて、つけていることを忘れるくらい自然な装着感が得られるのは、骨伝導イヤホンならではの大きなメリットです。
ヘッドホン難聴(イヤホン難聴)のリスクが抑えられる可能性
ヘッドホン難聴やイヤホン難聴という言葉をご存じでしょうか?
私自身、以前はあまり意識していなかったのですが、長時間イヤホンやヘッドホンで大きな音を聴き続けることで、聴覚にダメージを与えるというリスクがあります。これは、内耳にある「有毛細胞」という音を感知する細胞が、強い音の刺激で壊れてしまうことで起こる感音性難聴の一種です。
そして一度壊れてしまった有毛細胞は再生せず、失った聴力は基本的に元に戻ることはありません。
とくにリモートワークの普及により、イヤホンやヘッドホンを長時間使用する人が増えている現在、より多くの人が注意すべき健康リスクになっていると感じます。
では、骨伝導イヤホンを使えばこのリスクが完全になくなるのかというと、そうとは言い切れません。
ただし、骨伝導イヤホンは鼓膜を介さずに音の振動を直接骨を通して伝えるため、同じ音量でも音を“聴く”ために必要な出力が小さく済む傾向があります。

骨伝導イヤホンのデメリット
ここまで、メリットについて書いてきましたが、ここからは骨伝導イヤホンのデメリットについて、書いていきます。
音楽鑑賞による没頭感はやや薄れる
骨伝導イヤホンは耳の穴を使わずに音を聴く仕組みのため、一般的なカナル型やオーバーイヤー型のヘッドホンと比べると、音質面ではやや物足りなさを感じる場面があります。
とくに低音の響きや音の立体感、音場の広がりといった「ハイレゾ音源に求められるような没入感のある音のリッチさ」には欠ける印象があります。
そのため、音楽鑑賞において「高音質でしっかり聴きたい」「音の迫力を感じたい」といった目的で使用するには、やや物足りなさを感じるかもしれません。

とはいえ、骨伝導イヤホンでも音楽は十分楽しめますし、音が極端に悪いわけではありません。「作業中のBGMとして流す」「通勤・通学中に軽く聴く」「リモート会議で相手の声を聞く」といった音質への強いこだわりを求めない使い方であれば、非常に実用的で快適に使えるイヤホンです。
音質に関しては感じ方に個人差があるため、「クリアな音より臨場感を重視する人」や「重低音好きの人」には向かない可能性もある一方、「耳の負担を減らしたい」「ながら聴き中心の用途」にはぴったりというように、利用目的によって向き不向きが分かれるタイプのイヤホンといえるでしょう。
音が漏れることがある
意外に思われるかもしれませんが、骨伝導イヤホンでも音漏れは発生します。耳をふさがない構造である一方で、骨に振動を伝える際に外部にもわずかに音が響くため、音量を上げすぎると周囲に音が聞こえてしまう場合があります。
特に注意が必要なのは、朝の通勤電車などの静かな環境です。自分では気づきにくいですが、ボリュームを上げたまま使用していると、周囲の人に音が漏れて不快感を与えてしまうこともあります。
私自身も気づかないうちに、隣の人に聞こえていた…という経験があります。
ただし、周囲がある程度騒がしい場所や、歩行中・屋外などでの使用であれば、音漏れはあまり気にならないレベルです。密集した場所で長時間立ち止まって使うときや、静かな室内での使用には注意が必要ですが、それ以外では通常のカナル型イヤホンと比べて特別大きな問題になることは少ないと感じています。
このように、骨伝導イヤホンは構造上音が出ないわけではないという点を理解しておき、使用環境に応じた音量調整を意識することが大切です。
骨伝導イヤホンAfterShokzはバランスがよく使いやすいイヤホン
以上、今回は、骨伝導イヤホンAfterShokzについて書いてきました。ぜひ、実際に装着感など試せる機会があれば、装着して試聴されることをお勧めします。


